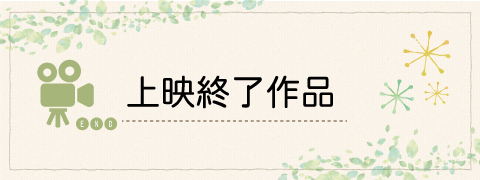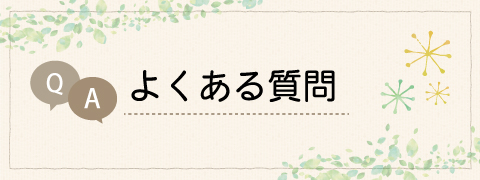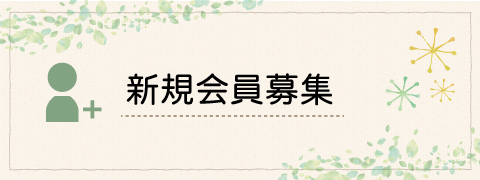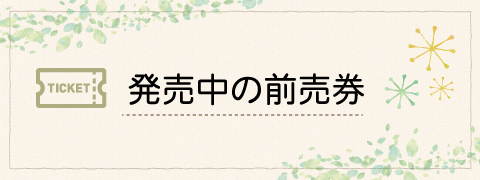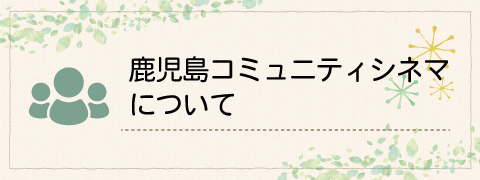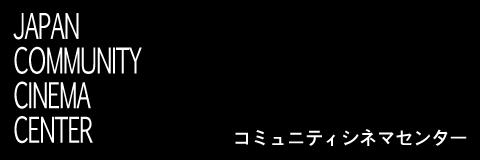第百話 いちばん静かな北野武
文:しばたけんじ
(鹿児島大学教員/哲学)
夏といえば、海である。それで、夏の映画にはよく海が出てくる。北野武がはじめて撮った『あの夏、いちばん静かな海』(1991)の海は、サーフィンをする海だった。 5、6人のサーフィン仲間以外には誰もいない砂浜に、真木蔵人がやってくる。聾唖の青年で、ゴミの収集を仕事にしている。粗大ゴミで拾ったサーフボードをもって、ひとりでサーフィンをやりにきたのだ。 そのうち、恋人の大島弘子がついてくる。彼女も聾唖である。だから、二人のカットに台詞はない。ただ二人で海にやってきて、黙々とサーフィンをやり、何もいわずに二人で帰っていく。 例のサーフィン仲間たちは、仲間内でこの二人を話題にし始めるが、自分たちの仲間に入れようとはしない。つてのない初心者が、自力で何かをはじめるというのは、まさにこういう感じである。 それは、ある種の孤立感として経験される。こういう経験を眼に見えるように撮るということは、きわめて高度な技術を必要としている。はじめて映画を撮った人間に、どうしてこんなことができるかといえば、才能としか考えようがない。 ところで、初心者が仲間に入るには、とりなす人間がいるものである。たまたま練習を見にきたサーフィン専門店の店主が、この二人の存在に気づき、面倒を見てやろうという気をおこす。 いや、店の客であるサーファーたちに面倒を見させようと思う。たんなる店主ではなく、地元のサーファーの先輩で、サーファー仲間には兄貴分同然なので、命じられれば面倒を見ざるをえない。 こうして二人は仲間に入る。が、何となく疎遠な感じである。これ以後、聾唖のカップルがサーファー仲間たちにとけ込めないままでいっしょに行動することが、物語を生み出していく。 たとえば、大会に申し込んで、みんなといっしょに現地入りしたはいいが、自分の名前を呼ぶアナウンスが聞こえず、出場を逃してしまう。その件で兄貴分の店主がサーファー仲間を叱るが、そのことが二人の孤立感をますます引き立たせる。 たんなる初心者だからではなく、やはり聾唖者であるがゆえに、一般社会から孤立せざるをえないということを、こういう形で示す演出は見事というほかない。ところが、二人の心中を暗示するラストシーンで、この構図が逆転する。 誰にも見ることのできない二人の世界が中心にあり、一般社会はその局外者として疎外される。二人の世界がどんな世界だったかは、観客にも分からない。監督の北野武にも分からなかったはずである。

あの夏、いちばん静かな海。
| 監督・脚本 | 北野武 |
|---|---|
| キャスト | 真木蔵人、大島弘子、河原さぶ、藤原稔三、鍵本景子、小磯勝弥 |
| 作品情報 | 1991年/日本/101分 |
聾唖の男女が織りなす恋愛模様を綴った、北野武監督第3作。 北野作品唯一のラブストーリーであるが、言葉による説明を一切排し、主人公たちを覚めた視点で捉えるなど、既存の恋愛映画とは一線を画した仕上がりになっている。 “キタノブルー”と称される透明感のある映像や省略の妙も秀逸。また、本作が初参加となった久石譲の哀しいメロディが心に染みる。